
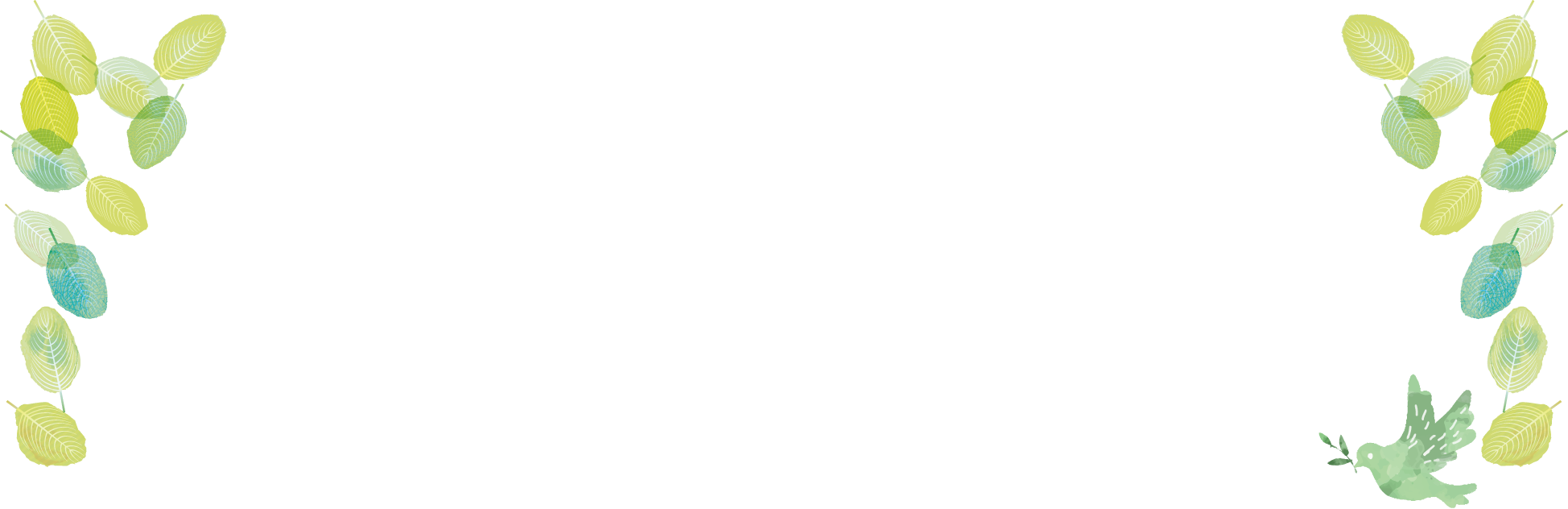
11月9日(日)参加者15名は、ガイドさんと共に名古屋城内を巡りました。
名古屋城は金鯱城の異名を持ちます。鯱城学園の名もこれと関連があるようです。
人出が予想より大幅に少なく、ゆっくりと見学できたのは雨の恵みか。(ポジティブシンキング?)
今回、石垣と本丸御殿上段之間、障壁画にスポットライトを当ててみました。
本丸御殿入り口付近の石垣~諸大名は貢献の証を家康に示すため、石材に何藩が集めたかがわかる刻印を刻んだのです。
写真は薩摩藩島津家の家紋。「丸に十文字」
上洛殿・上段之間~徳川3代将軍家光の宿泊のため築造。
家光の長女・千代姫は尾張徳川2代藩主・光友の正室で、婚礼の際に用いられた調度品は「初音の調度」と呼ばれました。
今年の春、徳川美術館で「初音の調度」国宝70点が公開されたのは記憶に新しいところです。
対面所・障壁画
尾張徳川家初代藩主義直の正室で春姫の故郷、和歌山県和歌の浦の風景が描かれています。
来年3月15日(日)には、「春姫まつり」が催され時代行列(春姫道中)が名古屋の街を練り歩きます。
一度ご覧あれ!
菊花大会は今年で78回と長きにわたり受け継がれてきた伝統を感じます。
わが西こじょう会の犬飼孝二、早川よしゑお二方が出品されているエリアは、一般的な菊とは異なり盆栽仕立ての山菊が所狭しと並んでいました。
その可憐で優美な姿に心惹かれました。
菊といえば「うつろい菊」が思い浮かびます。
秋から冬に菊が一瞬、紫色に変色し美しさが再度花開くこと。平安貴族はこれを愛でました。
また、「私はまだきれい、再度きれい」といった訴えかけにもなっているようです。
菊は薬草としても利用されました。
古来、長寿を願って菊の花弁をうかべた菊酒をのんだり、女性は菊花においた露を綿に含ませ肌をぬぐったりもしました。
菊には不老長寿をもたらす力があったと信じられていたのです。
日本酒の銘柄に菊とつくのが多いのは、こんなところに由来があったのですね。
「名古屋城と菊花大会」見学の報告
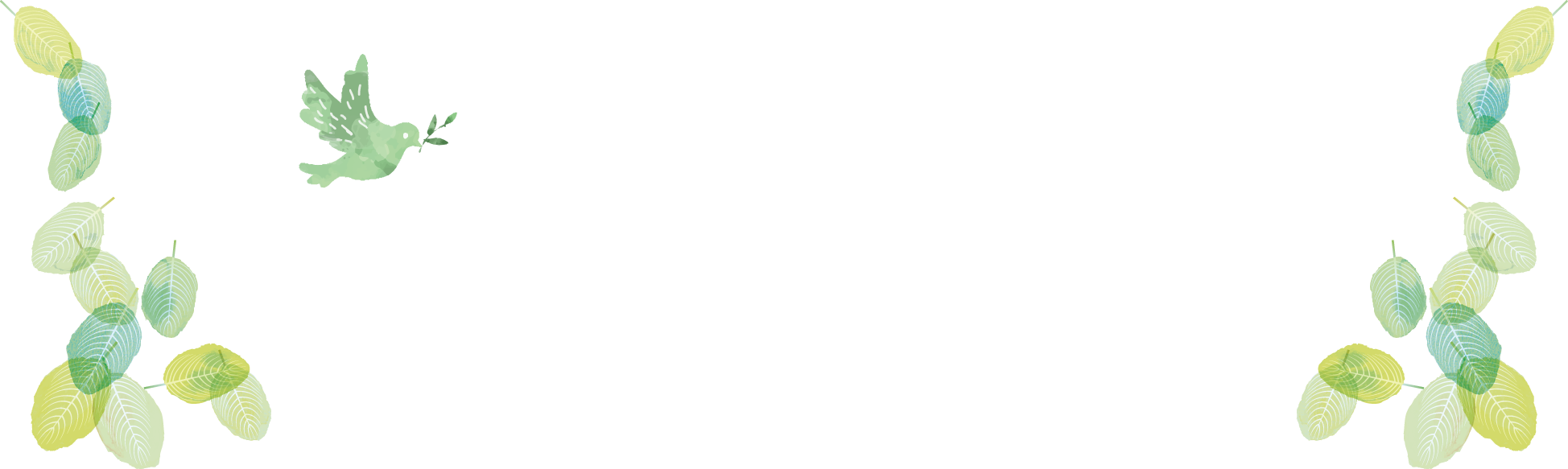
コメントを残す